生きものを意味する「Bios」と場所を意味する「Topos」を合成した、ギリシャ語を語源とするドイツ語です。直訳すると「野生の生きものが くらせる場所」となります。
※ドイツは歴史的に環境問題への意識が高く特に酸性雨での被害以降、先進的な取組みを行っています。

「ビオトープは子供にとって良いものです!」
園児にとって『身近に』生き物とふれあえる場所があることは本当に幸せだと、環境学習の際にいつも感じます。 好奇心旺盛で純粋な探究心を持つこの年頃の園児にとって『ビオトープ』に触れることは、環境や生き物に対する意識の向上、また『生』に対する尊厳や友達に対する『愛情』を育み「狂暴性」を持ち合わせない子供になるとも言われています。 自然や環境や人にやさしい園児育成の一助になるよう、ビオトープづくり計画を実践します!
「その園にあったビオトープづくりの計画をします!」
ビオトープをつくり、維持して行くうえで、保護者や先生等の理解と協力が不可欠です。まずは、園児、先生、保護者を対象とした「ビオトープとはどんなものか?」といったわかりやすい勉強会を開きます。 その後段階を経て、どんなビオトープにしたいか?どんな生き物が来て欲しいか?などをみなさんで一緒に考えます。 できあがった草案が、園内で実現出来るのか?出来ないのか?を、周辺環境や生き物の特性を考慮した上で精査しその園にあったものを共働で作っていくようにします。
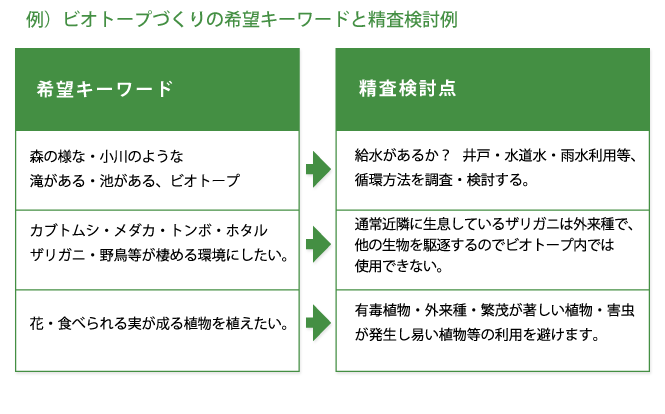
「親子のふれあい協働作業」
協働作業でビオトープをつくる事で、親子のコミュニケーションが図れます。その上、友達との連携を学び、自分たちで造った達成感を得ることが出来ます。弊社のビオトープづくりの経験を活かし、無理や危険な協働作業を緩和してできるだけ楽しく最後までお付き合いいただけるような方法で実施します。
- 素材の耐久性が良好である事
- 素材の毒性を検証する事
- 素材・構造が強固である事
- 耐風対策をとる事
- 病害虫対策をとる事
- 流亡等周辺環境に出来るだけ悪影響をおよぼさない事 等
弊社社は環境に配慮し安全性を1番に考えて計画・作業を行います。

役割分担の明確化・協働作業

完成後の愉しく学べる観察会

捕まえた生き物を調べる

様々な生き物とのふれあい

多様なビオトープ作成例:ユニット型田んぼ

多様なビオトープ作成例:高床式

